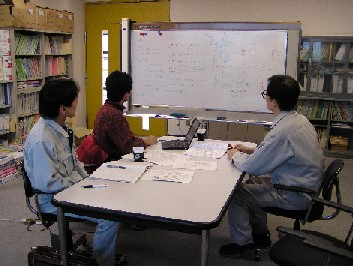| 部署 |
相談内容 |
相談の結果 |
その後の対応 |
| 加工 |
メッキなどの非常に薄い部分の硬さを知りたい。 |
ナノインデンター(超微小硬度計)を使用して、数十から数百nmの硬さの測定を行いました。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
製造現場で用いているゲージを定期的に検査したい。 |
三次元測定機で寸法精度を検査し、その結果を記した試験成績通知書を発行しました。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
プレス成型品の寸法精度を確認したい。 |
非接触三次元測定機を用いた寸法測定結果を提供しました。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
開発した製品の強度を調べ、取引先に提示したい |
大型構造物試験機で荷重試験を行い、その結果を記した試験成績通知書を発行しました。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
樹脂板から任意形状を切出したい。 |
加工図面をいただき、CADCAMによってウオータージェット加工プログラムを作成し、形状切出しを行いました。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
ネジの捩じ切れトルクを調べたい。 |
トルク試験機によって、捩じ切れトルクを測定しました。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
プラスチック部品を傷つけずに表面の粗さを測定したい。 |
微細形状測定装置を使用して、10uNの測定力で、表面の粗さとうねりを測定しました。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
シリコンのウェーハを精密に切断したい。 |
ダイシングソーを使用して、所望のパターンに切断しました。 |
 |
設備利用 |
| 加工 |
自分のアイデアを形にするデバイス開発をしたい。アドバイス等が欲しい。 |
共同研究を行いながら、研究資金情報提供など起業するまでのアドバイスを行いました。 |
 |
共同研究 |
| 加工 |
デバイスの試作プロセスを考えたのですがアドバイスが欲しい。 |
プロセスチャートを見せてもらい、問題点、改善点等を指摘して、施設利用などで効果を確認していただきました。 |
 |
設備利用 |
| 加工 |
金属部品の硬さを比較したい。 |
ビッカース硬度計を用いてビッカース硬度を比較しました。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
金属部品の変色部の成分が知りたい。 |
EPMAにより元素分析を行い、変色箇所と変色していない箇所に含まれる元素の違いを確認しました。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
材料の弾性率を測定したいのですが、どのような方法がありますか。 |
引張試験による測定のほか、超音波法による非破壊測定が可能です。超音波法では、常温から最高800℃程度まで温度を変化させながら測定可能です。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
表面硬化のための熱処理を行いました。その効果を確認したいのですがどのような方法がありますか。 |
最も簡単な評価法としては、表面からの硬さ試験(HRC)があります。また、内部の詳細な評価法としては、断面における硬さ分布測定のほか、金属組織の観察があります。X線マイクロアナライザー(EPMA)により、各元素の分布状態も確認できます。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
異なる条件で加工した金属製品の、粗さの比較を行いたい。 |
表面形状測定装置を用いて粗さを測定し、その比較を行いました。 |
 |
依頼試験 |
| 加工 |
部品の寸法(長さ、角度、半径等)が知りたい。 |
測定顕微鏡を用いて寸法を測定しました。 |
 |
依頼試験 |
| 材料 |
自社製樹脂製品の従来品と新製品の強度を比較したい。 |
試験体数が限られていたため、最も効率的な方法を検討し、強度試験機で圧縮試験を行いました。 |
 |
依頼試験 |
| 材料 |
金属製品の破損した原因を知りたい。 |
亀裂の方向や進展具合などから大きな力(衝撃力)による破損であることを説明しました。 |
 |
情報提供 |
| 材料 |
アルミ製の部品が磨耗した原因を特定したい。 |
磨耗部の組織観察と硬度測定を行うとともに、元素分析を行いました。組織観察および硬さ測定では原因を特定できませんでしたが、元素分析では特定の成分が規格値よりも少ないことがわかりました。 |
 |
依頼試験 |
| 材料 |
ゴムの硬度試験について知りたい。 |
試験方法、試験機等の説明を行いました。当該JISが最近改正されたので、旧JISとの違いについても説明しました。 |
 |
情報提供 |
| 材料 |
製品に付着した微小異物が何か調べたい。 |
赤外分光分析、拡大観察により特定され、成形加工時に混入したものと判明しました。 |
 |
依頼試験 |
| 評価 |
大判小判を発掘したが、本物であることを確かめたい。 |
蛍光X線による半定量分析の結果、期待される金・銀の含有量が確認されたので、本物であるか可能性が高い。 |
 |
依頼試験 |
| 評価 |
セラミックス製品の表面が変色したので原因を調べたい。 |
SEM分析、XPS分析やX線回折による表面分析法を説明し、適当な分析方法を検討した。まず、SEM分析により元素分析を行い組成を調べたが、有意な差が無く、最終的にXPS分析により窒化が原因であることを突き止めた。 |
 |
依頼試験 |
| 評価 |
食品中に繊維状の異物が混入していたので、これが何か調べたい。 |
赤外分光分析により、繊維状異物は綿であることが判明しました(依頼試験:有料)。 |
 |
依頼試験 |
| 評価 |
鋳造品の内部欠陥の有無を知りたい。 |
X線探傷装置により、鋳造品に内部欠陥があることを確認しました。 |
 |
依頼試験 |
| 評価 |
絶縁板が規定値以上の抵抗値を有しているか知りたい。 |
ディジタル超高抵抗計を用いて試験を行うことで、規定値以上であることを示しました。 |
 |
情報提供 |